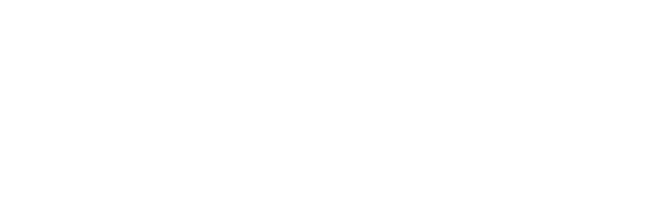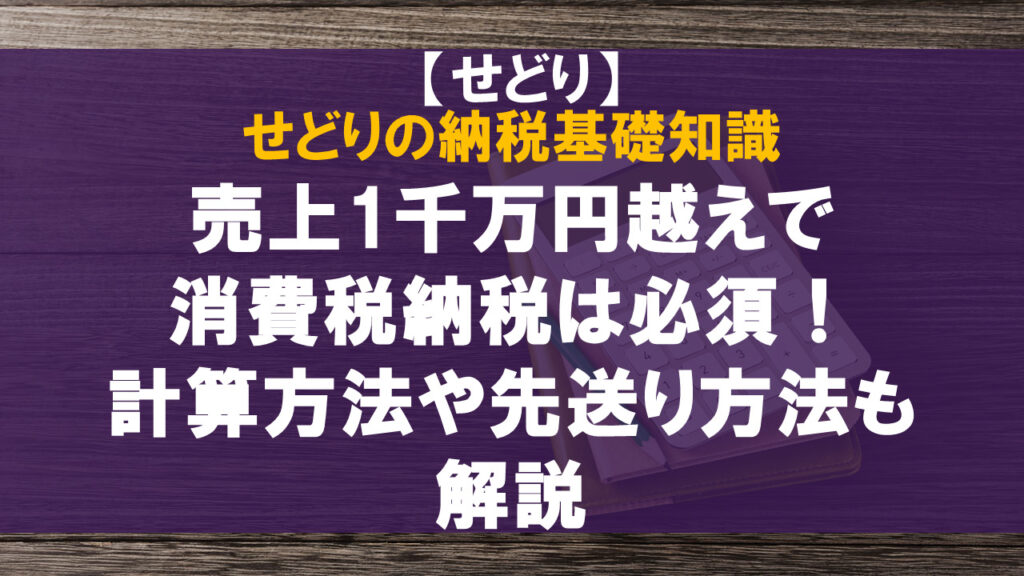
2022.07.30 投稿
2024.04.06 更新
せどり売上1000万超えで消費税納税は必須!計算方法や先送り方法も解説
この記事では、せどりでの消費税納税についての計算方法や先送り方法を解説します。
売上が1,000万円を超えた人が知っておきたい、消費税の条件や納税方法も紹介します。できれば消費税を支払いたくないと考える人も、詳細を確認しておきましょう。
当メディア(物販ラボ)では1000名以上の方に転売・物販の指導実績があり、こちらの記事はネット販売の経験が8年の経験と知見による内容になっています。
記事の最後では「ネット販売スタートマニュアル」を配布しています。ぜひ最後まで読んでいただき、活用してください!

物販ラボ運営責任者、アマラボ(物販ツール)の共同開発者、Amazon、ebay、Yahoo!ショッピング、ヤフオク、BUYMA、メルカリ、ラクマ、ヤフオクフリマ、Mercadolibre、etsy、BONANZA、ネットショップとあらゆる販路で販売。
SNS:Twitter・LINE
中川 瞬のプロフィール
目次
せどりで消費税納税が必要になるタイミング
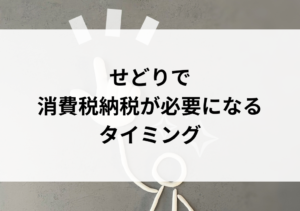
イントロダクション
せどりで初めて1,000万円の売上が出たら嬉しいでしょう。しかし、1,000万円を超えたら消費税納税のことも知識として取り入れなければなりません。
ですが、税金のことはわかりにくいのではないでしょうか。すべて税理士にお願いすることもできますが、自分でも基礎知識を理解しておくと、消費税に対する不安が軽減されるでしょう。
せどりで消費税納税が必要になるタイミング
まずは、消費税納税が必要になるタイミングについて、詳しく見ていきましょう。せどりの売上が1,000万円を超えたあたりで、薄々と消費税納税の必要性を感じているとは思いますが、改めてそのタイミングを理解しておいてください。
売上1,000万円超で課税事業者に
| 年間売上 | 消費税納税の義務と種類 |
| 1000万円以下 | 免税事業者 |
| 1000万円超 | 課税事業者 |
| 5000万円以下 | 課税事業者(簡易課税制度) |
| 5000万円超 | 課税事業者(本則課税) |
消費税納税が必要ないのは、「免除事業者」に該当する場合です。
免除事業者とは、年間の売上が1,000万円以下の場合に該当します。
ただし、せどりの年間売上が1,000万円を超えたからといって、すぐに消費税納税義務が発生するわけではありません。
消費税の納税の判断基準には「準備期間」があるからです。
準備期間は、個人事業主なら前々年までで、法人は前々事業年度まで。
個人事業主としてせどりをやっているなら、確定申告する年より2年前の売上が準備期間です。
たとえば、令和4年に確定申告をするなら、令和2年の売上が1,000万円を超えているか?が重要になってきます。
課税事業者になるタイミング
消費税の納税が必要かは2年前の売上を準備期間とすると説明しましたが、課税事業者になるタイミングで迷うかもしれません。
令和4年に確定申告をする場合を例にすると、3つのパターンがあります。
令和2年は準備期間で、この年に1,000万円超の売上があれば令和4年に消費税の納税が必要となります。また、令和2年に1,000万円以下の売上であっても、翌年の令和3年に1,000万円を超えると同じく消費税の納税が必要です。
つまり、準備期間に1,000万円超となるか、特定期間に1,000万円超になると、課税事業者となります。
課税事業者になったら、消費税の納税時期についても確認しておきましょう。
個人事業主は翌年の3月31日までですが、法人は課税期間末日の翌日から2か月以内です。
確定申告についてはこちらの記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
・(関連)せどりの確定申告はいくらから?確定申告が必要なケースとやり方
せどりの消費税の計算方法
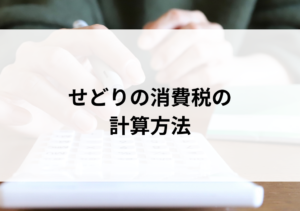
1,000万円以上の売上があったら、消費税を納税しなければなりません。
具体的にいくらの納税が必要かは、計算式に当てはめるとわかります。
- 本則(原則)課税
- 簡易課税
計算方法は、この2種類を活用してみてください。
本則(原則)課税方式
課税事業者になったときは、以下の本則(原則)課税方式で計算してください。
「消費税納税額=売上にかかる消費税額-仕入れにかかる消費税額」
【売上1000万円の場合】
| 粗利率 | 仕入額 | 売上にかかる消費税 | 仕入れにかかる消費税 | 消費税納税額 | 売上比率 |
| 10% | 900 | 100 | 90 | 10 | 1% |
| 20% | 800 | 100 | 80 | 20 | 2% |
| 30% | 700 | 100 | 70 | 30 | 3% |
| 40% | 600 | 100 | 60 | 40 | 4% |
| 50% | 500 | 100 | 50 | 50 | 5% |
(単位:万円)
売上比率で見ると、1%~5%くらいが目安になります。
粗利率が低ければ仕入れ額が高くなり、仕入れにかかる消費税額が高くなるため、消費税納税額の割合は少なくなります。
ただし、粗利率が50%と仕入れ額に対して利益の割合が高くなれば、後で支払う消費税納税額の割合が高くなるため注意するようにしてください。
本則(原則)課税方式による計算だと、粗利率に影響されるようになります。
仕入れの段階では消費税納税額は分からないので、どのくらいかかるのか分かりにくいかもしれません。
簡易課税方式
簡易課税方式では、次の計算式に当てはめて計算します。
「消費税納税額=売上にかかる消費税額-(売上のかかる消費税額×みなし仕入率)」
【売上1000万円の場合】
| 粗利率 | 仕入額 | 売上にかかる消費税 | 仕入れにかかる消費税 | 消費税納税額 | 売上比率 |
| 10% | 900 | 100 | 90 | 10 | 1% |
| 20% | 800 | 100 | 80 | 20 | 2% |
| 30% | 700 | 100 | 70 | 30 | 3% |
| 40% | 600 | 100 | 60 | 40 | 4% |
| 50% | 500 | 100 | 50 | 50 | 5% |
(単位:万円)
本則(原則)課税方式に比べて、簡易課税は簡単な計算方法です。
仕入れ額に対する消費税額を計算する必要がなく、みなし仕入れ率で計算します。
「みなし仕入れ率」は業種ごとに何%なのかが決められており40%~90%までで、せどりは小売業にあたるため80%となります。
100%-80%となり、20%が消費税納税額です。
簡易課税だと納める消費税額が一律になり、分かりやすいと感じるでしょう。また、本則(原則)課税方式のように粗利率の高さで割合が高くなることがなく、簡易課税のほうがお得だと感じるかもしれません。
実は、一概にはいえないため注意するようにしてください。
簡易課税がお得になるのは、支払った消費税が少ない場合です。
たくさんの仕入れをすれば、受けとった消費税に比べて支払う消費税額が多くなるため注意しなければなりません。最終的にどちらがお得なのかは、判断が難しいのではないでしょうか。
だからこそ、消費税の支払いは税理士にお願いしている人が少なくありません。
計算が面倒だと感じたら、税金の専門家である税理士に依頼することも考えておきましょう。
せどりで消費税を支払わないとどうなる?
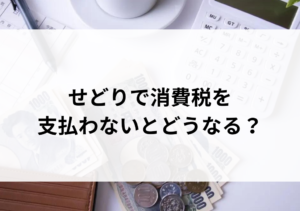
消費税の納税は、課税事業者になってから2年後に発生します。
せどりで安定した売上があればいいのですが、事業が上手くいかないと消費税を納税できないことがあるかもしれません。
期日まで納税できなかったら、約1か月程度で督促状が届くようになります。
さらに納税しないでいると、電話や書面で催促されるため注意しましょう。
場合によっては、税務署の担当者が直接会社に訪問することもあります。
税務署から督促状が届いた段階で、税務署は納税者の財産の情報を収集します。
何度催促しても納税しないときは、最終的には差し押さえになるでしょう。
真っ先に狙われるのは、現金・株・債券などの金融資産です。
勤め先の給与も差し押さえの対象となり、ある日銀行口座から預金がなくなる恐れがあります。
また、注意したいのが納税の義務は金額の額は関係ないことです。たとえ少額の税金を納めなかったとしても、差し押さえの対象となってしまいます。

せどりで消費税が支払えない時の対処法
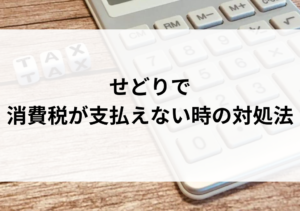
消費税の課税事業者になったら、税金を納める義務が発生します。しかし、せどりの利益が不安定だと、消費税を支払えなくなるかもしれません。
万が一そのような事態になったら、どう対処すればいいか確認しておくといいでしょう。
猶予申請する
納税の義務があるのにそのまま放置すれば差し押さえとなりますが、何らかの事情があるなら相談は可能です。まずは、税務署に相談しに行きましょう。
条件を満たしている場合は、納税期間を延長することができます。
猶予期間は原則1年となるため、納税が難しければ相談してください。
具体的な条件は以下のような内容があります。
- 前年同期と比較して20%以上減少している
- 一時的に納付することが困難な状況である
徴収窓口に相談
猶予期間が終了すると、納税しなければなりません。
期限内に納税できないときは、期限が切れる前に徴収窓口へ相談してください。
状況によっては、延滞税が軽減される場合があるため、早めに相談しましょう。
期限が切れて納税しないときは、催促されることになります。
差し押さえとなるリスクがあるため、まずは相談することを忘れないでください。
融資を受ける
猶予期間が与えられないときは、融資を受けることを考えるかもしれません。
しかし、銀行や日本政策金融金庫からの融資は、納税状況を把握されるため、融資を受けることは無理だと考えておきましょう。
融資の方法としておすすめなのは、不動産担保ローンやリースバックです。
不動産を担保にすれば貸し倒れリスクがないため、融資を受けやすくなります。
また、不動産担保ローンは金利が4~10%で、金利を抑えられるメリットもあります。リースバックも不動産を担保にする方法で、融資方法としておすすめです。
せどりの消費税納税で困らないためのアドバイス
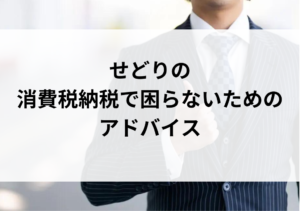
せどりの売上が伸びてきたら、そろそろ消費税納税のことを考慮しましょう。
納税できなくなるリスクを避けるため、早めに情報収集しておくと安心です。
法人設立で2年間免税される
せどりの売上が1,000万円を超えると消費税納税義務がありますが、さらに2年期間を延ばす方法があります。それは、個人事業主から法人になることです。
せどりの売上が1,000万円を超えたら、翌々年に法人化しましょう。
この方法ならさらに2年間消費税を支払う必要はなくなります。
また、法人化すると節税できるメリットもあります。
個人事業主だと累進課税のため売上が伸びるほど税金が増えますが、法人化すれば税金が安くなりお得です。所得が900万円を超えたら法人化がおすすめです。
・(関連)せどりビジネスで法人化するタイミングとメリット・デメリット
簡易課税方式の方が安くなりやすい
一般的には、簡易課税方式を選ぶと、消費税納税額が少なくなります。
ただし、必ずしも安くなるわけではないため、事前に確認がおすすめです。
一度選択した方式は2年間変更できないので、選択する前に税理士へ相談すると安心でしょう。また、売上が5,000万円を超えると、簡易課税方式は選べません。
売上が伸びることも考慮しながら、最適な方法を選ぶようにしてください。
消費税分を毎月積立しておくと安心
消費税を支払えないリスクを防ぐには、毎月積み立てるのが一番です。
売上が出たら全額を仕入れに回すのではなく、売上の2%~5%を積み立てるようにしてください。
5,000万円未満であれば2%、5,000万円以上は5%が目安です。
できれば、消費税のための専用口座を用意しておきましょう。
毎月決まった割合の金額を移すようにすれば、間違って使ってしまう心配はありません。
せどりの消費税まとめ
せどりの事業が上手くいくようになったら、消費税の支払いに注意が必要です。
税金の支払いは言い訳ができないため、課税業者になれば義務だと思っておきましょう。
もし、消費税の支払いで心配な場合は、税理士への相談がおすすめです。
消費税の仕組みは複雑で分かりにくいので、多くの人は専門家にお願いしています。
全部自分でやろうとせずに、早めに相談するようにしましょう。
物販ラボでは「ネット販売スタートマニュアル」も無料配布しています。
- 仕入先と販売先
- 商品リサーチ方法
- Amazonアカウント作成
これからネット販売を始めるのに必須のノウハウをまとめています!興味のある方はぜひ下記からプレゼントを受け取ってください。
あなたにおすすめの記事
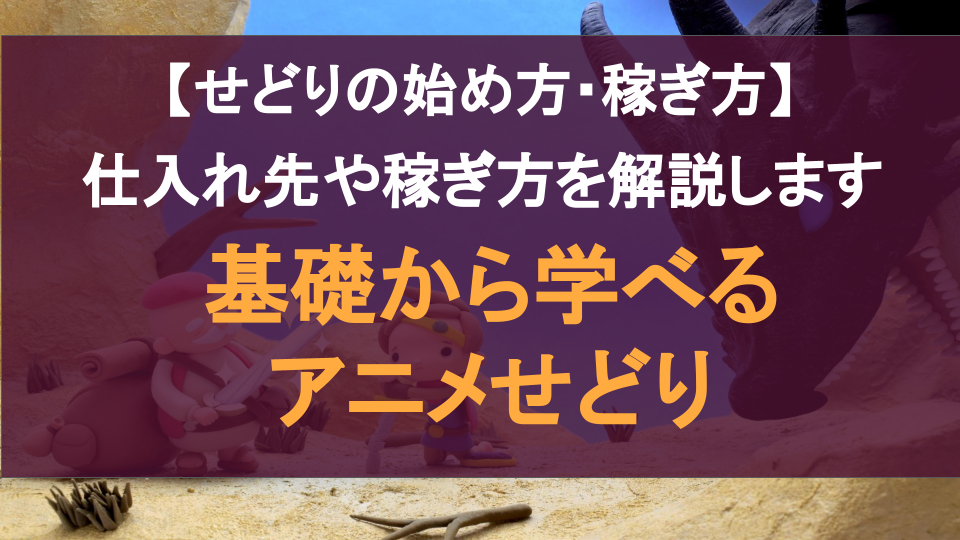
基礎から学べるアニメせどり【仕入れ先や稼ぎ方を解説します】
目次アニメせどりの仕入れ先アニメせどりの販売先利益商品のリサーチについてせどりの出品者の出品データを一括でリサーチできるツールアニメせどりのメリットとデメリットメリットデメリットまとめ アニメせどりの仕入れ先 アニメ商品...
2024.04.10 更新
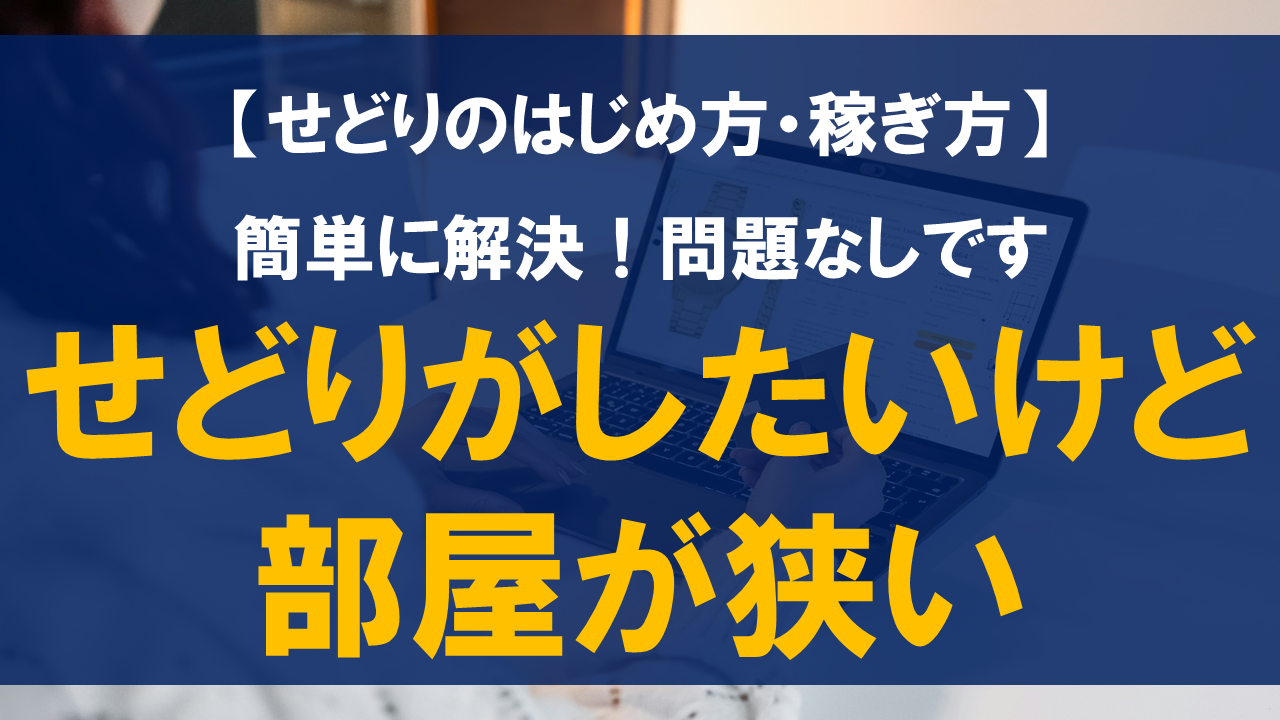
【簡単に解決】せどりがしたいけど部屋が狭い→問題なしです
目次【簡単に解決】せどりがしたいけど部屋が狭い→問題なしですAmazonのFBAサービスを使う小型の商品を中心にあつかうまとめ:せどりは部屋が狭い人でも稼げます 【簡単に解決】せどりがしたいけど部屋が狭い→問題なしです ...
2024.04.09 更新
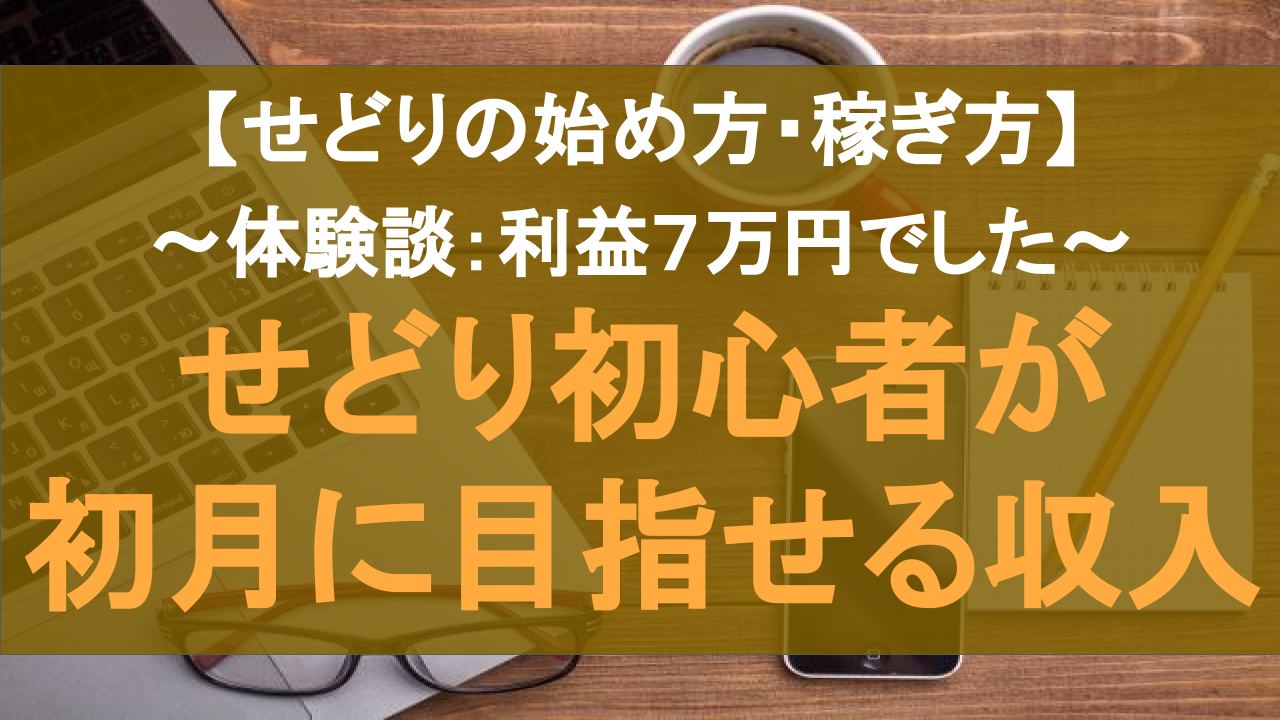
せどり初心者が初月に目指せる収入【体験談:利益7万円でした】
目次せどり初心者が初月に目指せる収入【体験談:利益7万円でした】僕の経験談:初心者が初月で利益7万円なぜ人によるのか?【考え方の話】まとめ:せどり初心者の収入は資金と行動次第です せどり初心者が初月に目指せる収入【体験談...
2024.04.09 更新
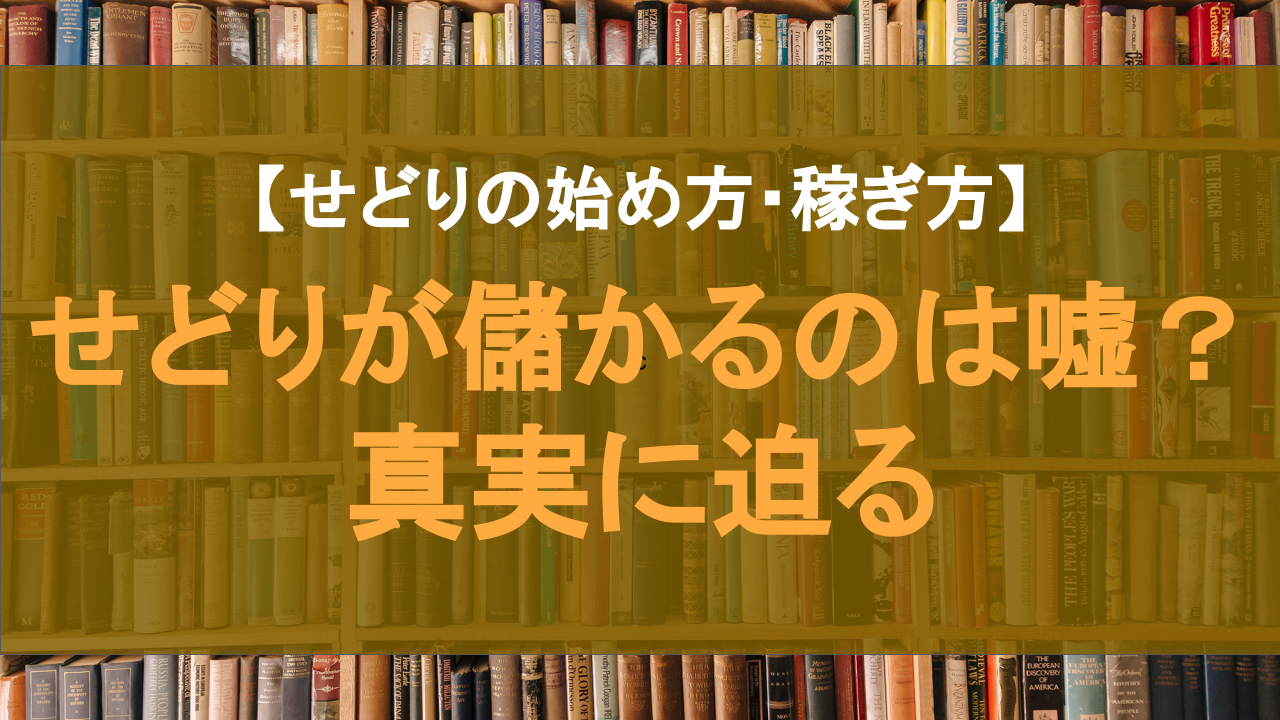
せどりが儲かるのは嘘?真実に迫る
目次せどりが儲かるのは嘘?真実に迫る儲かるかどうかは個人の取り組み方や努力次第市場の調査と商品の選定仕入れコストと販売価格のバランスリスク管理と効率化継続的な学習と成長まとめ:せどりが儲かるは嘘じゃないが個人の取り組み方...
2024.04.09 更新
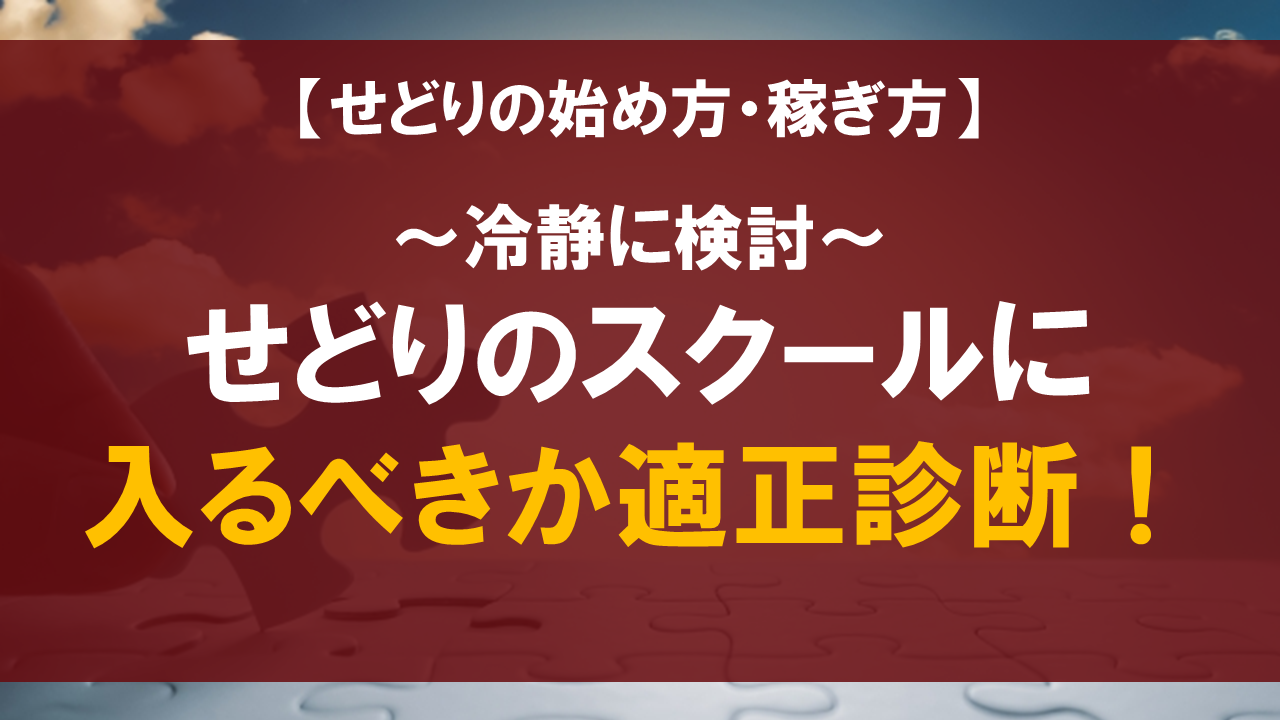
あなたがせどりのスクールに入るべきか適正診断【冷静に検討】
目次あなたがせどりのスクールに入るべきか適正診断【冷静に検討】せどりスクールのメリットせどりスクールのデメリット申込みに高額な費用がかかるケースが多い自己解決力が養われにくいコミュニケーションが苦手な人にはむしろ辛いまと...
2024.04.09 更新
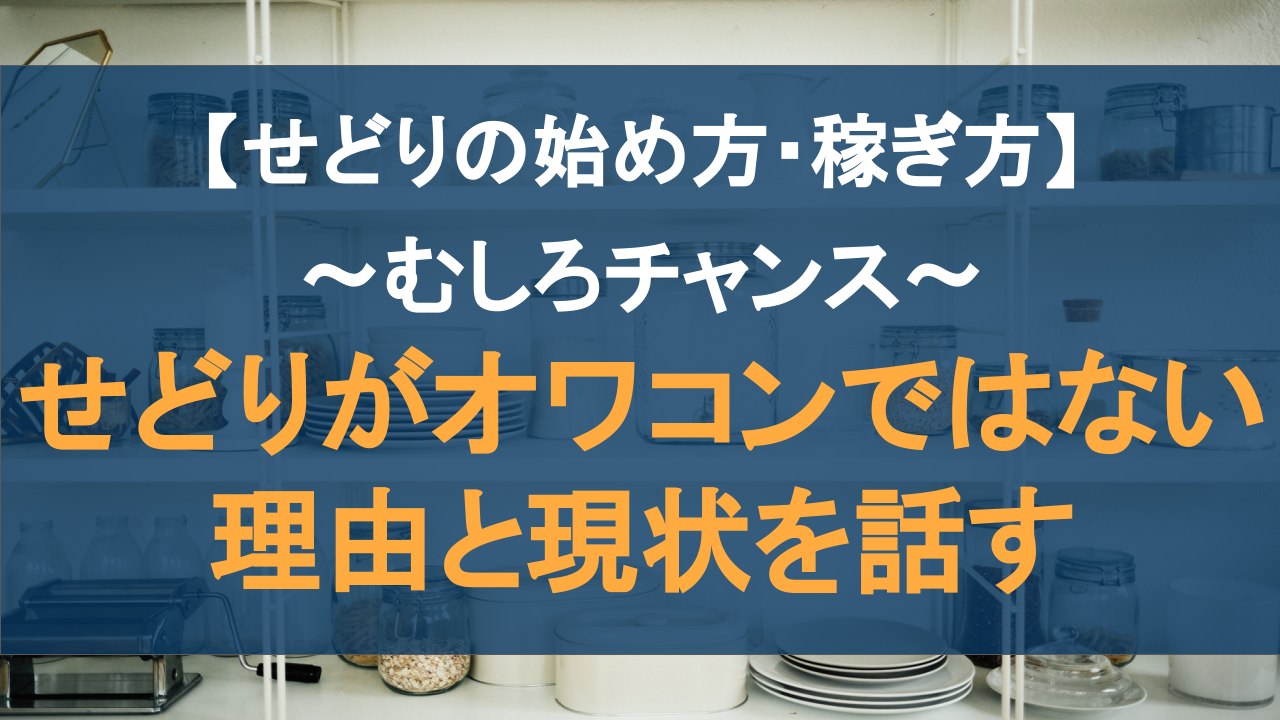
【むしろチャンス】せどりがオワコンではない理由と現状を話す
目次【むしろチャンス】せどりがオワコンではない理由と現状を話すなぜせどりはオワコンと言われるのか?極論:すべてのビジネスは「オワコン」と言われる説 【むしろチャンス】せどりがオワコンではない理由と現状を話す 結論から言い...
2024.04.10 更新
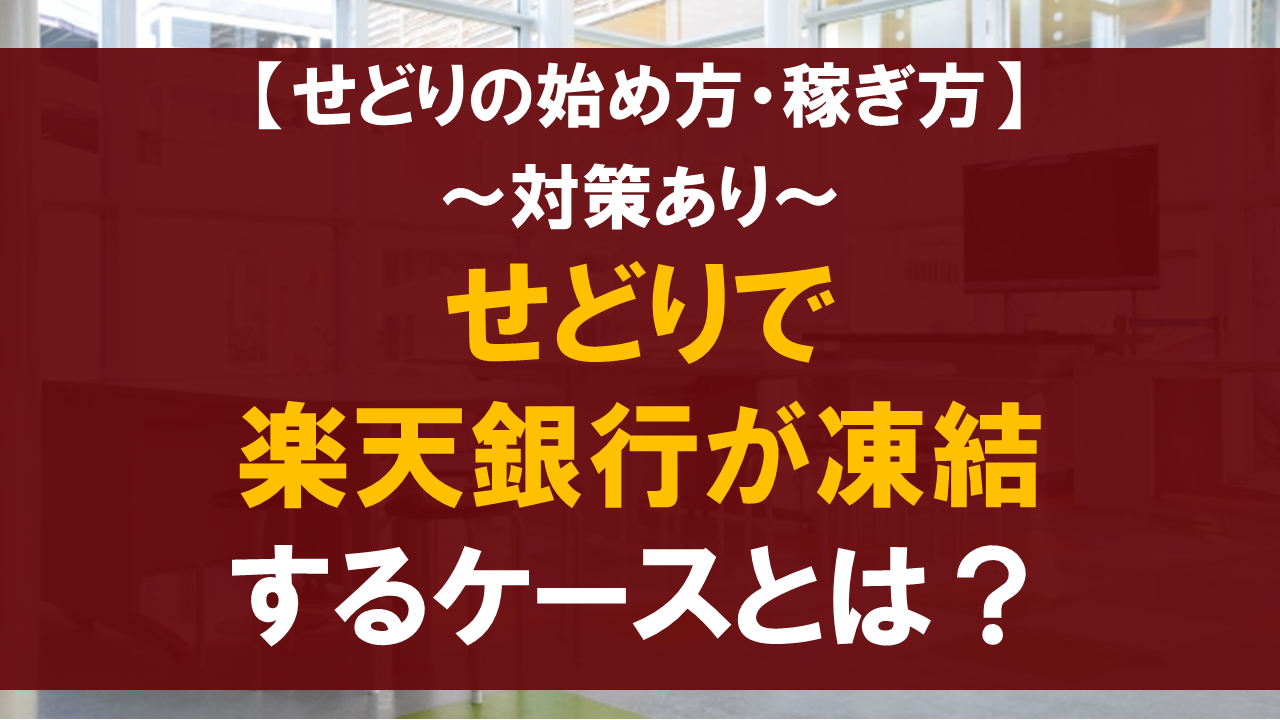
せどりで楽天銀行が凍結するケースとは?
目次せどりで楽天銀行が凍結するケースとは?イントロダクション複数アカウントでの取引大量の返品やクレーム不正な取引行為対策と注意点一つの口座を適切に活用する販売履歴の管理取引の透明性顧客対応の徹底まとめ:せどりにおける楽天...
2024.04.10 更新
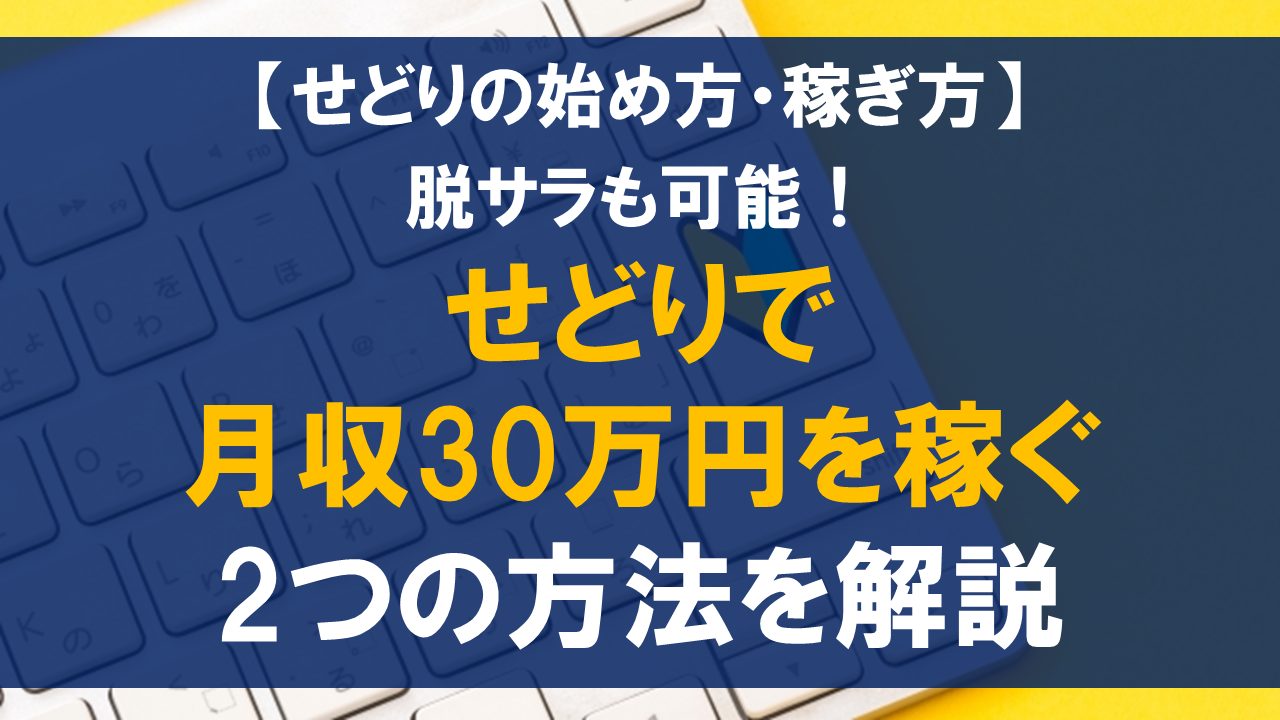
せどりで月収30万円を稼ぐ2つの方法を解説【脱サラも可能】
目次せどりで月収30万円を稼ぐ2つの方法を解説【脱サラも可能】せどりの売上だけで月収30万円をめざすせどりとせどりの情報発信で月収30万円をめざすまとめ:せどりで月収30万円をめざすなら情報発信も視野に せどりで月収30...
2024.04.10 更新
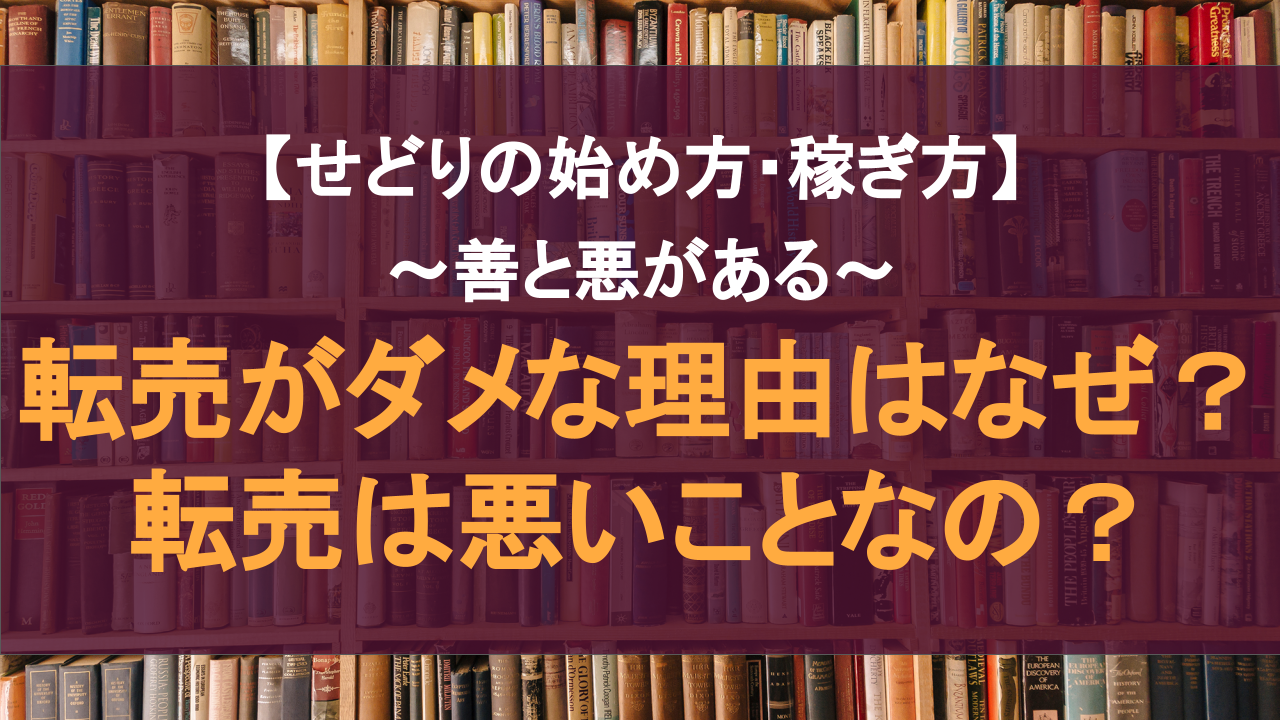
転売がダメな理由はなぜ?転売は悪いことなの?【善と悪がある】
目次転売がダメな理由はなぜ?転売は悪いことなの?前提:転売は違法ではない結論:転売がダメといわれる理由とは?転売は「すべてが悪」なのか?まとめ:転売がダメな理由は「ルール違反とマナー違反」です 転売がダメな理由はなぜ?転...
2024.04.10 更新